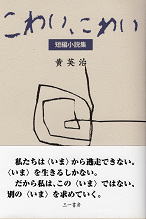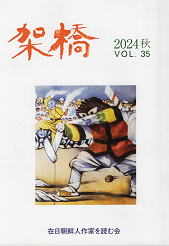|
黄(ファン) 英(ヨン) 治(チ)
|
|
|
|
|
|
1957年岐阜生まれ
「あばた」 第41回部落解放文学賞受賞 2015年
「壁を打つ旅」 第20回労働者文学賞(佳作) 2008年
「記憶の火葬」 第16回労働者文学賞 (入選) 2004年
季刊『千年紀文学』 連作「虹のしみ」連載中
|
|
|
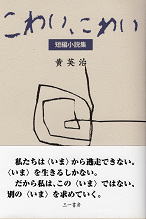 |
|
|
短編小説集『こわい、こわい』 (三一書房 2019年4月5日)
韓国語版 『あの壁まで』 (鄭美英訳 2019年)
韓国語版 『前夜』 (韓程善訳 宝庫社 2017年)
『在日二世の記憶』 (共著 集英社新書 2016年)
『前夜』 (コールサックス社 2015年)
『あの壁まで』 (影書房 2013年)
『記憶の火葬ー在日を生きるーいまは、かつての〈戦前の地で〉』
(影書房 2007年) |
|
|
|
|
|
【HPコラム 2025年4月】
朝鮮戦争を終わらせることについて
|
|
|
本稿の執筆現在、イスラエルとハマスのガザ戦争の停戦合意は破綻し、イスラエル軍のガザ地区および西岸地区、レバノン南部への攻撃が再開された。また、ウクライナとロシアの停戦をめぐっては、実現に予断を許さない状況にある。そうであるがゆえに、なおさら、戦闘を停止し、当該地域に暮らす人びとや戦闘員たちを覆う死の影を払い、民意と国際法に沿った公正な「平和」への第一歩となる両地域の「停戦」を願う気持ちはさらに強まる。
この思いに共感してくれる方は、決して少数ではないだろう。そこで私は、遠くのパレスチナ、ウクライナとともに、私たちの身近な戦争=朝鮮戦争の「停戦状態」が72年間そのままであることを忘れないで欲しい、とつけ加えたい。
「停戦」とは、「交戦中の両軍が何らかの目的のため、合意の上で一時的に戦闘行為を中止すること」(デジタル大辞泉)とされる。つまり、「停戦状態」とは「戦争状態の継続」ということになる。であるのに、日本の世論だけでなく、平和運動においても、「朝鮮戦争の(少なくとも)終戦」についての関心は低い。いや、ほとんどない、と言ってもいいだろう。
しかし、朝鮮戦争はいやでも、「日本の戦争」である。実際、横田基地には「朝鮮国連軍後方司令部」が置かれ、「国連軍地位協定」によって7か所(うち3か所は沖縄)の在日米軍施設が「朝鮮国連軍」の使用可能施設だ。「国連軍」の主力は米軍で、駐韓米軍・韓米連合軍司令官が「朝鮮国連軍」司令官を自動的に兼任する。つまり朝鮮半島で、朝鮮人民軍と米軍・韓国軍の間に、(ここ数年頻度を増している韓米+日の合同軍事演習を引き金に)なんらかの軍事衝突が起きれば、それはただちに朝鮮戦争「停戦」体制の崩壊となり、日本は自動的に「朝鮮国連軍」の後方基地としての機能を再開する(と見なされ)、当該の米軍施設は、朝鮮人民軍の攻撃目標となる(この部分は、高林敏之・立教大学非常勤講師のフェイスブック投稿を引用した)。
逆に、Imagine! 朝鮮戦争の「停戦」を「終戦」―平和協定の締結に導けば、朝米・朝日の国交正常化と、朝鮮と韓国の平和共存=漸進的な統一プロセスの軌道への進入によって、東アジアの冷戦はようやく終わることになる。そうなれば、実質的な軍縮=米軍の韓国と日本(=沖縄)からの削減―撤退、朝鮮人民軍・韓国軍・自衛隊の縮小の条件が整う。
ちょっと待て、中国の軍事大国化―海洋進出、台湾問題―有事の問題はどうする? との声が聞こえてくる。そうであったとして、どうして朝鮮戦争を終わらせてはならないのか!
パレスチナ、ウクライナ、そして世界各地の戦争―停戦状態が、一刻も早く公正な「平和」体制へと移行することを願う。その願いは、ただちに、朝鮮戦争を終わらせなければならないという、私(たち)の課題、それに寄与する仕事に参加する責任を生じさせる。
(3月24日記)
|
|
|
|
|
|
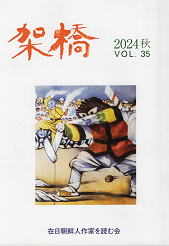 |
小説 「七月八日、猛暑日」
黄 英治
『架橋』VOL 35 2024秋
「在日朝鮮人作家を読む会」発行
500円 |
|
|
|
|
|
【HPコラム 2024・2】
ますます悪くなる、けれども
|
|
|
群馬県が1月29日、県立公園「群馬の森」(高崎市)にあるアジア・太平洋戦争で戦時強制動員(徴用、強制連行)された朝鮮人犠牲者の追悼碑を行政代執行で撤去した。その理由を山本一太知事は、25日の定例会見で、「設置の際に定めたルールに反したことがすべてだ」と語った。そのルールとは、「政治的行事を行わない」というものだが、「政治的行事」とされた2014年の追悼「式で『強制連行』という文言を含む政治的発言があり、碑は中立的性格を失った」とする東京高裁の判断を22年6月、最高裁が認めたことが根拠だ。ところで、こうした動きを後押ししたのが、歴史修正主義者・レイシスト団体らの組織的な県議会への「請願」や、執拗な街宣活動であったことは見逃せない。
大日本帝国は敗戦時、徴用工や軍隊慰安婦の強制動員(連行)の証拠を組織的に焼却した。にもかかわらず、それの資料(証拠)は多数発掘されており、これに基づく、「強制連行はあった」との学術的な評価も定まっている。なのに、司法が、このような証拠と評価に依拠した発言を「政治的」として封じ込め、慰霊碑や追悼碑などの歴史的建造物をふくむ記憶、追悼と反省・友好の空間を根こそぎする(東京・横網公園の関東大震災朝鮮人虐殺の追悼碑をめぐる攻防、強制連行についての解説文の改ざんなど――根こそぎしようとする)動きが日本各地で現実化している。
群馬の追悼碑は、土台さえもバラバラに砕かれ、瓦礫となった。ガザ市街のように――。
ガザでイスラエル国家(およびG7)によってほしいままにされている、誰の眼にも明らかなパレスチナ民族にたいするジェノサイド=民族浄化。しかし、それはG7の「国際社会」とメディアにおいては完全に「正当化」されている。昨年10月7日に敢行されたハマース(イスラーム抵抗運動)を中心にしたガザの戦闘員の越境攻撃でイスラエル側に千人以上の犠牲者が生まれたのは事実だ。しかし、なぜこの事態が生まれたのか、の根本原因である、イスラエルが1948年に、パレスチナの地に暮らしていたパレスチナ人の実に4分の3にあたる75万人以上を民族浄化して――パレスチナ人が「ナクバ(大災厄)」と名づけた記憶――建国された事実と歴史。引き続く絶えまない入植、占領、戦争、虐殺、差別、分断と隔離の日々=歴史が消され、あたかもすべてが10月7日に始まったかのように、イスラエルの「正当防衛」がまことしやかに語られる。そうしてガザで、子どもたちをはじめとして3万人におよぶパレスチナ人殺しが、制止もされず、日々実行されている。
植民地主義の歴史を抹消しながら民族浄化を「正当化」する、〈脱歴史化の政治〉が世界を覆っている。圧倒的な力関係の非対称のなかで、表現の自由か憎悪の煽動か、意見は偏っているか否か、と「バランスをとる」ことが強要される。しかし、圧倒的な力関係のなかでの「中立」とは、暗黙のうちに強者に加担することにほかならない。
記憶を他殺させない、自殺などしない。植民地主義への抵抗をあきらめない。連帯を求め、手を繋ぐ。沈黙しない。それが、この時代において〈人間であること〉の証しだ。ましてや、文学をあきらめず、信じているなら、ば――。
※本稿は『現代思想 02 特集*パレスチナから問う――100年の暴力を考える』(2024vol.52-2、青土社)の討論、論考、インタビュー、小説から引用し、参考にして執筆しました。多くの人が本誌をお読みくださるよう、心願します。
|
|
|
|
|
|
【評論・黄英治「頭蓋の虚点」】
「黄英治「頭蓋の虚点」(「労働者文学』92号)は、蔵書の断捨離に伴う見当識障害を引き金に、それでも忘却してはならない「朝鮮人」が「不逞鮮人」として虐殺の憂き目にあった負の記憶をこれでもかと幻視させるが、過去の著書の作品よりも、複数のイメージを連鎖させる技巧がいっそう丁寧で切実さもたたえ、忘れ難い衝迫力がある。
「〈世界内戦〉下の文芸時評 第105回 抽象化とニヒリズムのスパイラルを脱コード化する文学的多層性」 岡和田晃 『図書新聞』2023年12月9日号
|
|
|
|
|
|
【HPコラム 2023・1】
前期高齢者の断捨離 |
|
|
2022年11月、「前期高齢者」の仲間入りをした。日本国の社会制度に規定されて、ということなのだが、65歳は、50歳になったときよりも、還暦を迎えたときよりも、けじめ感が強い気がする。誕生日の数日前には介護保険証が届き、誕生日の前日には市役所で「国民」年金の請求手続きをした。それは人生のカウントダウンが確実にはじまったという実感をもたらした。生きていられる(だろう)時間の幅を、両親の享年を基に計ってみる。死は、間近ではなさそうだが、それほど遠くもない、ようだ。それで、年来口にしてはいたが、およそ実行しなかった、本の断捨離に手をつけることにした。
しかし、それぞれの本には、買ったときの、特に若い頃、金はないが何とか手に入れたという喜びや、送ってくれた人の気持ちが強く憑依しているようだ。断捨離にあたって、それを手元に置いておきたいという思いと、再読はしないだろうという予感がせめぎあって、肉体的にはもちろんだが、精神にもダメージを与えられた。
さようなら本たちよ。従属理論家たち、日本の進歩的政治、経済学者、思想家たち。岩波講座、東大出版会、○○現代史、現代社会主義講座、教育問題双書、大学で使った教科書、無名の詩人たち、読まれなかった同人誌、狭山裁判のパンフ、在日朝鮮人史研究会、書評誌、古い辞書たち……。
断捨離。岩波、三一をはじめとする新書たち。政治、経済、歴史、文学、文化、差別、宇宙、教育、ルポ、哲学、美術、音楽、LGBT……。知識はここからもらった。バーコードがついていない古い本は資源ごみ。バーコードがついているものはブックオフ。37点で375円。辛うじて牛丼食べられるか? ゆで太郎のかけそばには、5円足りない。
まだまだ続いた断捨離。岩波文庫、国民文庫、果てはレーニン全集の3分の2ほどが、マンションのごみ置き場に積まれた。
救いは、文学関係の本を、朝鮮大学校外国語学部(日本文学・植民地文学専攻)の教授が引き受けてくれたこと。林檎箱5つと、蜜柑箱4つを送り出すことができた。
まだ終わってはいない断捨離。ここまで作業して、ようやく本棚ひとつを、市の粗大ごみ処理に委ねることができた。本棚の上を埋め尽くしていた文庫、新書、雑誌は消え、二重に詰め込まれていた本はすぐに引き出せるようになった。もう新しい本はあまり買わないだろう。古くて大切な本、埴谷雄高、武田泰淳、ドストエフスキー、魯迅、在日朝鮮人文学……を、愛おしみながら、ゆっくりと、深く読む生活になるはずだ。
|
|
|
|
|
|
「庶民の尊厳と希望ー高琢基『緩やかな禍』を読む」 2022年
web労動者文学会作品集 (外部リンク)
|
|
|
|
|
|
【HPコラム 2021・6】
三日で二度のPCR検査 黄英治
|
|
|
腹部に違和を覚えたのは五月十七日の夕食後だった。右上腹部、押さえると肋骨にあたる。変だなぁ、とは思ったが、軽く考えていた。入眠後の夜半過ぎに激しい痛みが襲う。差し込みは背中の同位置にも。やがて全身の関節が強張り、寝返りを打つのも、息をするにも冷汗が滲み、胃が張る。だが吐き気はない。夕食の帆立刺身で食あたりか、と推定した。
十八日中は起きられず、呻吟しつつ胃 薬と整腸剤を服用した。口にしたのはごく少量の飯と汁だけ。痛みがやや緩和するが39度の発熱。根が神経質。ネット検索する。私と同症状の「急性胆のう炎は、放置すると重症化し、死に至ることもある」を見つけて震えあがった。自然治癒はない。十九日、意を決して、かかりつけの総合病院へ。熱がある。コロナチェックにかかるか? 正門の体温計測36度1分⁈ 問診票を詳細に書く。看護師が体温計を差し出す。万事休す! 38度9分。
こちらへ、と隔離。ここでお待ちを。内科医が来ます。ビニールで仕切られたスペースの壁に「対症療法しかできません」とある。半時間ほどで小太りの内科医が来て、PCR検査してもらい、薬を出します。それ以上のことはできません、と私の背中をさすり、十秒で消えた。看護師が鼻の奥へと検体採取のスワブを回転させながら挿入した。うぐぐぅ、と唸る。思った以上に苦しい。結果は先生から携帯に電話します。処方された薬は総合感冒薬と頓服。この処方で症状が改善するか、と薬剤師に医師への確認を依頼して帰宅。半時間後、頓服処方されているから、と薬剤師。二時間後、内科医から、陰性でした。服薬して様子を見てくれ、と。
翌日、頓服の効果か平熱になり痛みは治まったが、不安のなか悶々と過ごした。二十一日に再び外来へ。平熱、PCR陰性は錦の御旗。やっと消化器内科の医師の診察が受けられた。血液検査、CT撮影。そして医師の診断。ご心配の胆のう炎でなく、大腸憩室炎です。即入院して、絶食・点滴、抗生剤治療します。虚を突かれた。即入院、ですか? ええ、炎症数値が高いですし、早い方がいいです。PCR検査後、本院へ行ってください。あの、二日前にPCR検査陰性判定出ていますが……。決まりですから――。症状と苦痛に見合った治療を、発症後五日目にようやく受けられた。五泊六日の入院生活を経て二十六日、「無事」に退院した。 |
|
|
|
|
|
「新・狂人日記」 2019年
web労動者文学会作品集 (外部リンク)
|
|
|
|
|