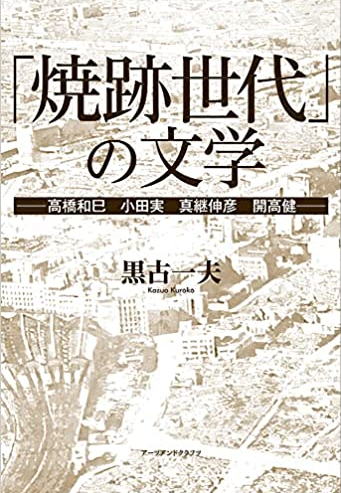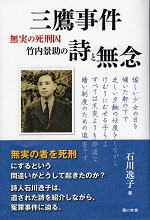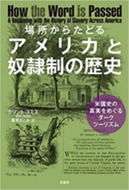会員推薦の本
|
|
|
栃木裕『屠畜のお仕事』を読んで 稲田恭明
東京都中央卸売市場食肉市場、いわゆる「芝浦屠場」で定年まで働いてこられた方の講演を先日お聞きする機会があり、大変興味を惹かれたので、その方、すなわち栃木裕さんの書かれた『屠畜のお仕事』を読んだ。イラストや写真とともに作業工程を細かく描いた作品で、「誌上での現場見学」を通じて、屠場で働く人々の喜びや充実感を知ってほしいとの思いで書かれた本である。栃木さんは退職後、小学校で子どもたちに授業を行う機会を得た際、子どもたちから「動物を殺すときにはどんな気持ちなのか」という質問をたびたび受けたそうだ。子どもたちに悪気はないとはいえ、その背景には屠畜を人の忌み嫌う仕事と捉える、社会に深く根付いた偏見があると考えた栃木さんは、こうした子どもたちからの問いに答えることを主な目的として本書を書いた。と同時に、栃木さんを本書執筆に駆り立てたもうひとつの動機は、屠畜について語る際に、「殺す」という言葉を避けて、「いのちをいただく」とか「生命を解く」といった言葉に言い換えることによって「免罪符」を得たかのように振る舞う風潮に対する強い憤りであったという。「いのちをいただく」と語る背後に存在する「いいわけ」こそが差別の根源だと考える栃木さんは、「屠場労働者に『免罪符』はいらない」、「動物を殺すことを忌み嫌う思想性」そのものを弾劾しようと考えた、というのである。
子どもたちの問いに戻ると、屠場では一つ一つの工程(例えば放血から胸割りとか、四肢の切除とか、頭の切除と皮むきとか、内臓摘出=「腹出し」といった各工程)には20秒という短い時間しか与えられないため、「動物を殺すときに考えること」は、「素早く、かつ丁寧に」、「ミスをせず」、「怪我をしないよう」、「衛生的に」と、多くのことに細心の注意を払いつつ、目の前の作業に集中することだという。少しでも注意が散漫になると大怪我につながりかねず、非常に高度な熟練の技術が要求され、それだけに、技術を向上させることへの喜びと達成感は大きく、やりがいのある楽しい仕事だったと栃木さんは語っている。本書の帯には、「栃木さんのナイフさばきを、現場で何度か見せてもらったことがある。その的確さ、無駄のなさ、息を飲むスピード感。とんでもない技術の精度が、彼の仕事と人生を物語っていた」という、エッセイスト・平松洋子さんの言葉が書かれている。屠場労働者の本音と、屠畜という仕事の持つ充実感が語られた貴重な本であると言えよう。
以上紹介した栃木さんの主張に異論はなく、多くのことを学ばせて頂いた。しかし、にも拘わらず、すべての疑問が氷解したとは言えない。というより、これまであえて目を背けてきた問いに改めて直面することになった。それは、子どもたちの問いに含まれていたであろう、「屠場で殺される牛や豚は可哀そうではないのか」という単純かつ直感的な疑問である。私は菜食主義者ではないし、人間が動物の肉を食べることが悪いことだとは思っていない。しかし、なぜ牛や豚や鶏は、人間に食べられるために飼育され、殺されなければならないのかという、子どもでも抱く疑問に対する答えが私にはわからないのである。言うまでもないことだが、これは「肉食」という思想とシステムの問題であって、誰が動物を殺すかなどという問題とは関係がない。「家畜は作物である」「牛や豚は経済動物であって、愛玩動物とは異なる」と栃木さんは言うが、この答えは私を納得させない。やはり自分で考え続けるしかないようである。
|
|
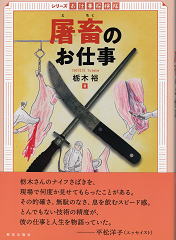
『屠畜のお仕事』
栃木裕 著
(解放出版社1600円+税)
|
|

「JR冥界ドキュメント」
ー国鉄解体の現場・
田町電車区運転士の一日〜
村山良三著
1800円+税
梨の木舎
|
|
書評 『JR冥界ドキュメント』を読んで 村松孝明
労働者の実質賃金は下がり続け海外に出稼ぎに出るほどの貧乏な国になりつつあるのに、防衛費は世界三位の軍事大国になろうとしている。アメリカの企業を買い占めるほどの勢いがあった時代もあったのに、なぜこんなことになってしまったのか……。国鉄解体の現場・田町電車区運転手の一日(村山良三著)のサブタイトルを付けた本書がヒントになってくれる。
国鉄の分割民営化に反対する国労の組合員だった著者は、東京駅から相模湾・駿河湾の海沿いを走る電車の運転手だった。それが分割民営化の過程で要員機動センターに送られ、草むしりや清掃や切符整理などの専門外の仕事につかされる。その40年近くも前の体験や見聞を明らかにしていく。まるで亡霊のような本が出た。しかし、亡霊と言って無視することはできない。衰弱した日本を労働者の立場から振り返るならば、国鉄の分割民営化が原点ではなかろうか。視点をそこに置くと見えて来るものがある。中曽根康弘が言う。「総評を崩壊させようと思った。国労が解体すれば、総評も崩壊するということを明確に意識してやった」。中心的な存在だった闘う国鉄労働者を解体させることで、総評を崩壊させ、総評が支えていた社会党を消滅させることに成功したのだ。自民党の一党独裁を可能にして、それが今日の日本沈没につながっているのではないか。企業であれ政府であれ対等な力を持った反対勢力がなければ、チェック機能がなくなり腐敗するのは明らかだ。その役割を果たしていたのが、闘う労働組合であり、その中央組織が総評であった。今の連合は政府に媚を売り、闘う労働者の足を引っ張るだけの存在になっていないか。
最近話題になっているのが兵庫県知事のパラハラ問題だ。カニやカキや革ジャンのおねだりなどを告発した人が、懲戒処分された。県は公益通報者を守るどころか、追い詰めて死に追いやった。それでも知事は辞める気はなさそうだ。国レベルで言えば裏金問題だ。裏金を使って次の選挙に当選することしか頭にないようだ。百年先の国の未来を考える政治家はいないようだ。これらは対等な力を持った勢力がなくなったために腐敗したのだ。
日本の軍国主義は闘う労働者を徹底的につぶした。敗戦後に乗り込んできた連合軍が真っ先に労働組合の結成を奨励した。民主主義にはまともな労働組合が必要だとわかっていたのだ。しかし、朝鮮半島の共産化が、日本の共産化を恐れて組合つぶしにかかったのが、下山事件や三鷹事件などの一連の事件ではなかったか。
本書では労働者はまとまらなければダメだということが強調されている。自分だけ生き残ろうとしたのでは当局の思う壺だ。足の引っ張り合いをしていがみ合っていたら、当局と対等に渡り合う力は発揮できない。ましてや労基法など全く無視して、国を挙げて襲ってきているのに組合は分裂し、対立していたのではどうにもならない。
労働者よ 団結せよ。亡霊の教訓だ。
陳腐だが間違いない。
(梨の木舎1800円+税)
|
|
【会員(穂坂晴子)推薦の本】 2023
「わたしの心のレンズ
現場の記憶を紡ぐ」
大石芳野
2022年6月12日
集英社インターナショナル
900円+税

|
|
【会員(三上広昭)推薦の本】 2023
「社会文学」第46号
特集「労働文学」成立百年
鎌田慧・楜沢健 他
2017年7月31日
日本社会文学会
不二出版

|
|
【会員(土田宏樹)推薦の本】 2022
「郵政労使に問う
ー職場復帰への戦いの軌跡」
池田実
2022年8月25日
すいれん舎
1760円(税込み)

|
|
【会員(沢村ふう子)推薦の本】 2022
「場所からたどるアメリカと
奴隷制の歴史」
クリント・スミス
原書房
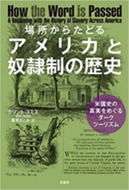
|
|
【会員(村松孝明)推薦の本】 2022
「焼跡世代」の文学
ー高橋和巳 小田実 真鍋伸彦 開高健ー
黒古一夫
2022年5月 発行
アーツアンドクラフツ
2680円
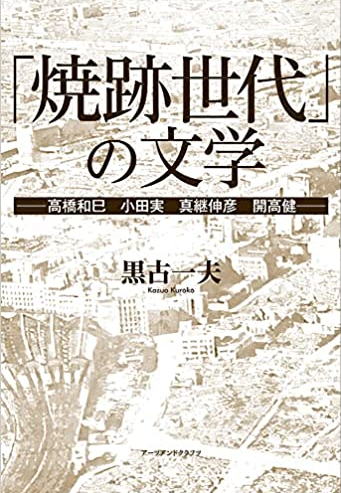
|
|
【会員(福田玲三)推薦の本】 2022
三鷹事件 無実の死刑囚
竹内景助の詩と無念
石川逸子
2022年3月10日 発行
梨の木舎
1200円+税
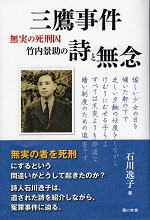
|
|